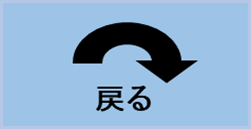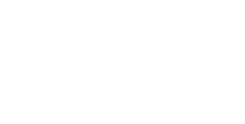さらに詳しく知りたい方・興味のある方はこちらをご覧下さい。
奈良へは何処から来たのか(徐福伝説)
この地域(豊橋)の人は、弥生期末に奈良から来た物部氏(あるいは安曇氏)であると書きました。それでは、奈良へは何処から来たのでしょうか。
1)徐福伝説
奈良の物部氏は、紀元前220年頃徐福と供に日本に渡来した集団の子孫と考えられます。徐福は秦始皇帝の命を受け、神仙を探しあて不老不死の霊薬を持ち帰るため、童男童女数千人と百工及び五穀の種を携えて日本にやってきました。しかし徐福は平原と広沼を得て王となり、秦国へは戻らなかったと司馬遷「史記」にあります。
2)徐福は何故日本に渡来したのか
中国では紀元前770年頃より約500年間戦乱が続きました。それは「十八史略」に述べられています。長年戦争が続いた理由は気温低下があったことが理由のようです。春秋時代と戦国時代を通じ、多くの国が戦い多くの国が滅んだ。その間、さまざまな悲劇が繰り返された。死した怨念の仇敵は、墓があばかれ屍に鞭打たれた。讒言や裏切りの発覚により自害させられ、その死体は馬の皮袋に入れられて、長江へ投げ捨てられた。
紀元前221年に秦が中国を統一し戦乱は終了したが、悲劇は続いた。人民は互いに監視させられ、密告を奨励した。他人の犯罪を告発しない者やかくまった者は厳罰に処された。喟水のほとりに罪人を裁判する場所があり、処刑された罪人の血で喟水は真っ赤に染まったという。また始皇帝陵や大宮殿の造営、万里の長城建設の労役が人民を苦しめた。
このような苛酷な世界を避け、生き残りのために集団移住するのが徐福の日本への渡来だったのではないでしょうか。徐福とその集団は、中国から来たと書きました。しかしその集団には漢民族は含まれていなかったと思われます。
NHKブック篠田謙一著「日本人になった先祖たち」によれば、ミトコンドリアDNA調査結果による、日本人中の漢民族の割合は1.2%程度だからです。
3)徐福は吉野ヶ里に定住した
『』内は七田忠昭和著「邪馬台国時代のクニの都 吉野ヶ里遺跡」による
徐福とその集団は、吉野ヶ里に定住したと考えられます。徐福が渡来したのは
紀元前3世紀と考えられますが、下記がその状況証拠です。
①『弥生時代前期後半(紀元前3世紀)になると、これまでの環濠跡の北方
170メートルの丘陵尾根に、大規模な環濠をめぐらせた本格的な環濠集落
がつくられる。』
②『吉野ヶ里遺跡ではさらにさかのぼった前期後半に青銅器製造を開始している
ことが確実になった。』また銅鐸も出土している。
③『前期後半の甕棺墓が、「志波屋四の坪地区」の南部で二基みつかっている。
これが、吉野ヶ里遺跡では現段階で確実な最古の墳墓ということになる。』②③は徐福が伴った百工を思わせます。
④徐福伝説の「上陸の地」や、徐福を祀る「金立神社」に吉野ヶ里が近いこともあげ
られます。
⑤さらに中国由来のV字形環濠集落、高床建築、米(プラントオパール)や絹、
中国江南の人に近い人骨の出土があり、多人数の渡来を裏づける圧倒的に多
い甕棺墓の基数もあげられます。
4)徐福集団の子孫は筑紫平野に広がり物部氏となった
(状況証拠を下記します)
①まず吉野ヶ里での青銅器鋳造年代は、上記3)の②より弥生前期後半です。
藤瀬禎博著「九州の銅鐸工房 安永田遺跡」によれば本行遺跡(佐賀県鳥栖
市)について『弥生時代中期前半~後半にかけて、青銅器をつくっていた
「工人の住む集落」があったものと判断できる。』とあります。さらに安永田
遺跡(佐賀県鳥栖市)について、『青銅器工房の時期は。
弥生時代中期末もしくはその直前と判断することができた。』とあります。
このように時代経過とともに、青銅器鋳造工房が筑紫平野に移動していっ
たように見えます。
そして谷川謙一著「白鳥伝説」によれば『太田亮の「姓氏家系大辞典」には、
物部氏の本貫を筑後平野と考え、高良神社はその氏神としている。高良神社
の大祝は鏡山家で物部姓である。』とあります。つまり吉野ヶ里から時代経
過とともに移動したように思われる筑紫平野が、物部氏発祥の地だと言うの
です。
②物部氏は銅鐸を作ります。徐福集団が住んだと思われる吉野ヶ里で銅鐸が出土
しています。徐福集団が吉野ヶ里から拡がったと考えられる筑紫平野の安永
田遺跡でも銅鐸鋳型が出土し、そこが物部氏発祥の地であるわけです。
③筑紫平野を発祥の地とする物部氏が、徐福伝説を持っています。
④徐福は百工を伴いましたが、物部氏も百工を思わせる金属工人を統率していま
した。鋳造師の「伊福部氏」、「ひとつ目の神」を信仰する鍛冶師、鉱山士の「穴
師」など。
5)徐福集団の子孫から発祥したと思われる物部氏が、遠賀河周辺に移動
(状況証拠を下記します)。
①谷川健一著「白鳥伝説」によれば、『鞍手郡宮田町大字磯光字儀長に天照神社が
鎮座する。祭神は天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(ギハヤヒの命)である。
社殿によると垂仁帝の時代に、鞍手郡宮田村の笠木山にニギヤハヒの神が降
臨したという。』とある。
②また同じく谷川健一著「白鳥伝説」によれば、『六ケ岳には宗像の三女神が降臨
したという伝承が残っている。山麓の鞍手町室木にある六ケ岳神社の祭神は
宗像三女神を祀り、土地の人は三柱様とよんでいるそうである。』とある。③上記①②の神社は物部氏の神を祀っており、物部氏が住んだと考えられる。
その神が降臨したと言うのですから、どこかから移り住んだと言っているの
だと考えられる。どこから来たのかと考える時に、物部氏発祥の地であり、
遠賀川周辺から近くである筑紫平野から来たと考えるのが妥当ではないか。
5)遠賀河周辺の物部氏が近畿へ移動した(状況証拠を下記します)。
①澤田洋太郎著「日本古代史の謎を解く」によれば、『北九州の遠賀川河口近くの
一帯に芹田物部・二田物部など物部系の地名がいくつもあり、河内・大阪方
面にも同じく芹田物部・二田物部がいたことを挙げ、物部族は九州から近畿
地方に東遷したという史実を実証的に説いている。』とある。
②「先代旧事本紀」の「天神本紀」には、物部氏の祖神である饒速日尊が多くの氏族
の祖を引き連れて、安曇氏を船頭と舵取りにして、大船団を組んで東遷した
様子が記載されている。
③田原本町教育委員会による「弥生の王都 唐古・鍵」によれば、『弥生中期中頃
には、多条の環濠が掘削されムラの姿は一変します。』とあります。弥生中
期中頃には、今まではなかった環濠集落が、唐古・鍵遺跡に出来たというの
です。環濠集落は吉野ヶ里と同じです。
また『鋳造に関連する工房があったと推定されます。』『銅鐸などの青銅
器は、・・・』とあり、青銅器の鋳造工房があり、銅鐸も鋳造していたとい
うことで、これも吉野ヶ里や筑紫平野と同じです。
6)豊橋周辺の人はどこから来たのかのまとめ
中国から来た徐福集団が、吉野ヶ里、筑紫平野と移動して物部氏となり、奈良に移動した。その奈良から 東海地方に展開し、豊橋に来たのだと考えます。