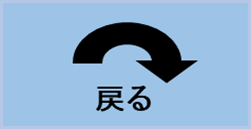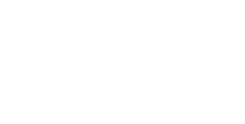「石巻さまご来山の話」という説話が、豊橋市立石巻中学校による「弓張風土記」にあります。それによると概要は以下の通り。
『昔、石巻さまは、長彦、伊豆彦の両神をおつれになり、大和の国三輪山から陸路紀伊の国に出られ、それより舟で三河湾にお入りになり、老津に上陸、それから牛の背にお乗りになって、三輪山と地形山容ともよく似た石巻山に居を定められたといわれております。』とある。
この説話は何か歴史的は背景があるのか、神郷地区にお住まいの方の御好意で見せて頂きました石巻神社に関する資料と、佐野康一著「神ケ谷郷土史」を参照して調べました。
1)石巻さま(参照した資料では石巻大明神)とは
石巻大明神とは、第42代文武天皇の若宮の武児親王のようです。「左遷の難候て」とあり、当地に来た理由は、政治闘争のなかで左遷されたようです。代42代文武天皇は天武天皇の系列で、次の代43代元明天皇は天智天皇の系列ですので、天武系から天智系に変わった際の左遷と思われます。若宮の武児親王(石巻大明神)は、石巻神社上社、下社と長孫(おさひこ)天神社に祀られています。

2)伊豆彦・長彦(おさひこ)とは
神ケ谷郷土史によれば「舎人長日子・出日子」とあります。舎人とは、皇族や貴族に仕え、警備や雑用などに従事した者とありますので、2人とも若宮の武児親王について来た、身の回りを世話する人のようです。
「伊豆彦の宮は神ケ谷村にあり」(神ケ谷郷土史より)との事で、今は篦矢神社の摂社に坐す。長彦については、「長比古は我大祖也宮は長彦村の則神也」とあり、長孫天神社に坐すと思われます。しかし長孫天神社は、祭神が少彦名命で、内陣は二社造り。左に石巻大明神 右に菜宮大明神とあります。
石巻大明神が武児親王とすれば、二社造の右に長彦が坐すのか、あるいは少彦名命が坐すのか不明です。(二社造りのどちらかの相殿として長彦が祀られているのか?)