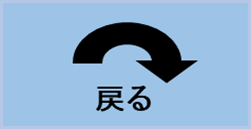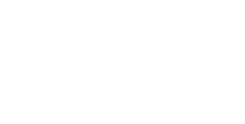【石巻神社上社管粥祭】(校区のあゆみ 石巻より)
『陰暦正月14~15日に行われていたが、現在は2月第2の土日に行われている。一年の作物のでき具合を占う行事である。
神主は祝詞を奉読して祈祷する。炊煮を司る神主が石を打って神火をとり、かなえの下に用意した薪に火を焚き付ける。湯が沸騰すると18本の管に印を付けて粥の中へ入れる。祈祷が続く中、神主を時折榊の枝で作った三つ叉で粥と管をかきまぜる。
朝6時、火を消して冷めるのを待って、管の中の粥の多少や水分の有無、粥つぶのかけ具合、色の可否、形の様子などを調べる。その結果から農作物の豊作か凶作かを占う。作物ごとに上中に区別し、作付けの参考にする。
作物 大麦 小麦 米(早、中、晩) 大豆 小豆 稗 胡麻
蕎 大根 黍 大角豆 麻 芋子 粟(早、晩)』
管の材料について、石巻神社は葦を使い、砥鹿神社は竹を使うとの事。
(神郷の方より)
【同様の神事】
①砥鹿神社(愛知県豊川市)の粥占祭 (砥鹿神社 由緒書より)
『一月十五日午前八時早朝神水にて粥を炊き上げ、これへ農産物・海産物の名を印した竹の管二十七本を混ぜて攪拌する。この後宮司は各々の竹の管につまった粥の量を卜定し、その年の天候や作物の豊凶を占う。
凍てつく寒さの中行われる粥占祭は、古くより「オタメシ」「オクダガイ」
として親しまれ、粥占符を求めて三河はもとより遠州や尾張地方からも参拝者が訪れる。』
②登彌神社(奈良県奈良市石木町)の粥占い (登彌神社 由緒書より)
『登弥神社ではもとは小正月の行事でしたが、今は二月一日に行います。氏子が毎年交代で、早朝から、米・小豆と、青竹の筒三七本を束ねたものを、湯釜で炊きます。一時間あまりで竹筒を引き上げ、農作物の品目ごとに竹筒を割り、粥の入り具合でその年の作物の良否を占います。』
③諏訪大社下社春宮(長野県)の筒粥神事 (諏訪大社 由緒書より)
『神楽殿の左方にある筒粥殿は、毎年正月14日夜から15日の朝にかけて筒粥神事を執行するための神粥炊上げの社殿で、土間の中央にある石の円形のいろりは江戸時代初期のものと言われている。大釜の中に米と小豆それにアシの筒を入れて一晩中炊き続け、筒の中に入った粥の状態に依って、その年の農作物の
豊凶を占うもので、時代により作物の種類と品数は異なりますが只今では43種の作物と世の中全般を1本、計44本の筒が使われます。その占いの正確なこと、神占正に誤りなしと七不思議の1つに挙げられています。』
【考察】
上記した通り4つの神社において、いずれも管と粥を煮て、管への粥の入り具合で作物の豊凶を占う農業神事が行われている。この4つ神社の間に、何か共通点や関係性があるのでしょうか。考察を行いました。
1)豊橋の神社と祭神を調べた結果と、石巻神社は物部氏四代当主大木食命が孝
安天皇の御代に勧進したということより石巻神社およびその周辺には、物部
氏がいたと考えられます。
2)次に砥鹿神社であるが、祭神は大己貴命で物部氏が祀る神である。また「先代
旧事本紀」の「国造本紀」によれば、参河国造は物部連の祖出雲色大臣、五世の
孫知波夜命とある。国造と一之宮には深い関係があると思われるので、参河
国一之宮砥鹿神社とその周辺には物部氏がいたと考えられる。
3)奈良の登彌神社については、祭神が物部氏の祖神の饒速日命であり、登彌神
社とその周辺には物部氏がいたと考えられる。
ここで東海の物部氏は、弥生後期に奈良を出て東海に展開したということな
ので、3)の奈良の物部氏が行っていた神事が、東海に人の移動と供に伝わ
り、1)石巻神社、および2)砥鹿神社へと引き継がれたと考えられる。
4)諏訪神社については、諏訪大社上社前宮、本宮の周辺に小さな神社が散在し
ており、それが「神長官 守矢資料館 周辺ガイドブック」に記載されている。
それによると「霊石」の祭神は大国主命、神明社の祭神は市杵島比売命、下馬沢
社の祭神は金山彦と少彦名命、疱瘡神の祠の祭神は少彦名命で、磯並山神の祭
神は大山祗命または日月神で、所政社の祭神は不明で一説にはスサノオ・大己
貴命、子安社の祭神は豊玉姫命、相本社の祭神はイザナギ・イザナミ、鶏冠社
祭神は不明・一説には大国魂命などで、物部氏の祀る神(青字)と安曇氏が祀
る神(赤字)である。
このことから、諏訪地方には物部氏と安曇氏がいたことが考えられる。これら
の事から考えると、弥生時代末期に奈良から出て東海に展開した物部氏が諏訪
地方に来て住み、筒粥神事を持って来て伝えたのではないかと考えられる。